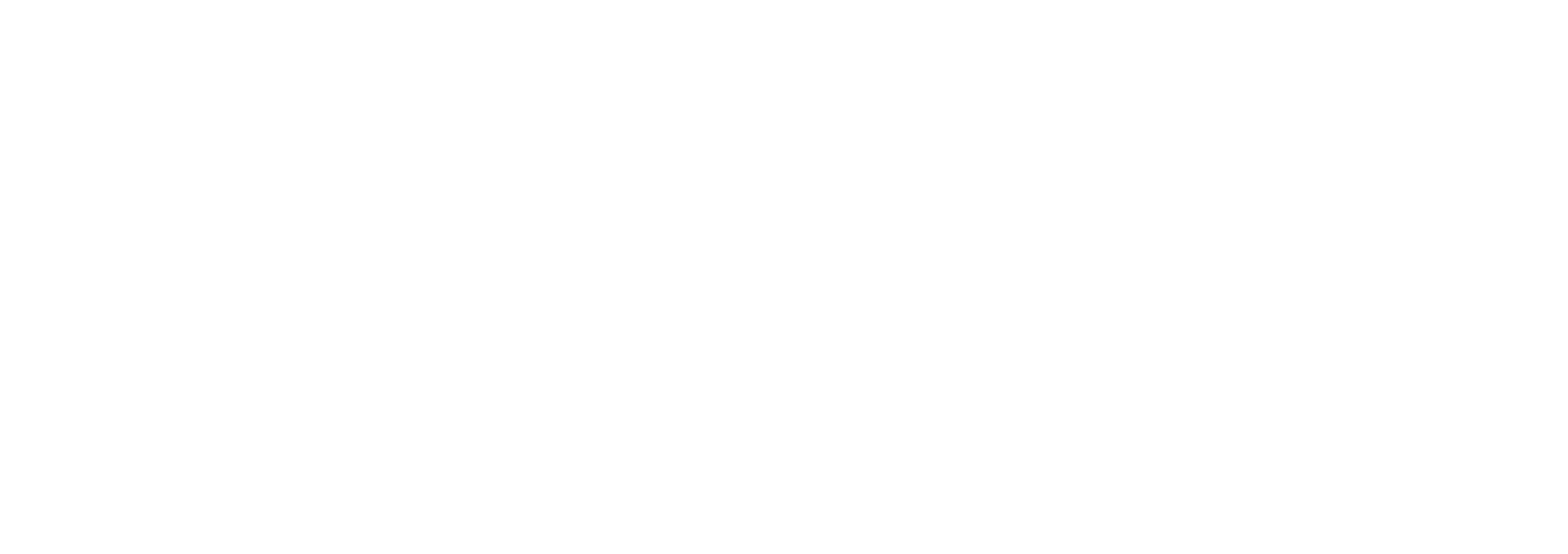外構は、家の顔とも言える大切なスペースです。その外構がオープンな状態だと開放感にあふれ、より広々とした印象を与えます。しかし、そのメリットと同時に不意な侵入対策や視線からのプライバシー保護といった課題にも気を配る必要があります。特に、お盆の時期には不在が多くなり、空き巣のリスクが高まるとされています。それらをどのように対策すれば良いのでしょうか?
この記事では、外構・エクステリアによる侵入防止と防犯対策について、具体的な例とともにご紹介します。
目次
オープン外構のメリット・デメリット
「オープン外構」とは、フェンスや塀が低く、あるいは全くない状態で、敷地が道路や隣地と直接つながっている状態=開放的な外構を指します。広々とした駐車場や庭を演出したい場合、敷地全体を活用したい場合に選ばれています。
この開放感こそがオープン外構の醍醐味であり、その最大のメリットと言えるでしょう。広々とした視界が生まれて自宅全体が一望できることは、新築の家で敷地全体を有効活用したいと願う方々にとって魅力的な選択となります。
オープン外構のメリット:開放感とシンプルなデザイン
開放感
オープン外構は塀やフェンスに囲まれないため、外から見ても家全体が一望できる広々とした空間になります。新築の家で敷地全体を広く使いたい、という方々に最適です。
シンプルなデザイン
シンプルな外構は住宅そのものや庭の植栽、花壇や植木鉢やプランターなどを置いて、個性的な空間を作り出すことができます。
オープン外構のデメリット:防犯面の懸念とプライバシーの確保
防犯面の懸念
オープン外構では敷地内が開放的すぎることから、人の出入りを防ぐ効果が薄れ、子供やペットでも容易に侵入することができたりします。
プライバシーの確保
あまりにオープンだと、外からの視線が気になってしまうでしょう。その結果、せっかく大きな窓を設けても、常にカーテンを閉めっぱなしの状態が続いてしまうことになります。
オープン外構を悩ますお盆休み
2023年のお盆は、8月13日(日)~16日(水)までの4日間が基本的なお盆休みです。11日は「山の日」の祝日、12日は土曜日なので、土日祝がお休みのお勤め先では、11日(金)~16日(水)までの6連休が期待できます。
お盆は先祖を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な時間。しかし、家族が集まる機会が少なくなった最近は、お盆は家族が集まる貴重な機会となり、その機会に合わせて、出向いたり招いたりして過ごす時間が多くなりました。
空き巣が増える?:防犯対策の重要性
お盆の時期は多くの人々が休みを利用して帰省やお出かけするなど外出が多くなり、数日間、自宅を空ける機会も増えるため、留守を狙った犯罪も増加する傾向にあります。
YKK AP株式会社による防犯対策に関する記事に掲載されている犯罪傾向のデータによると、侵入盗犯者には以下のような行動パターンがあります。
侵入盗犯の行動パターン1:まず留守を確かめる
侵入盗犯は、まず目的の家が留守かどうかを確認します。インターホンを鳴らしてみたり、家の中に人の動きがないか、カーテンのしまり具合、たまった郵便物など、外から見える家の様子も留守確認の手段となっています。
侵入盗犯の行動パターン2:窓から入る
侵入経路はというと、戸建て住宅の約60%が窓から。その中で最も多いのが直接庭に出入りできる「1階居室の窓」からの侵入です。侵入口は次に表出入口、その他出入口の順で多く、2階建て以上の戸建て住宅の90%が1階から侵入されているという報告もあります。
侵入盗犯の行動パターン3:5分であきらめる
侵入に時間がかかればかかるほど、用心深い侵入盗犯は犯行をあきらめます。侵入をあきらめる時間で、最も多いのが2~5分。つまり5分以上要すると、侵入をあきらめる確率が高いのです。
では、これにどう対処すれば良いのでしょうか?
特に、門扉や塀を設けてなくて、庭や駐車場や玄関が道路から丸見えのオープン外構の家では、侵入を防ぐ方法や家を空ける際の防犯対策を考えることが求められます。
オープン外構の侵入防止・防犯対策
基本的な防犯対策
効果的な防犯対策の一部を以下に紹介します。
対策1:近隣住民への連絡
長期間、家を空ける際は、隣の方に事前に伝えるのも一つの方法です。不審な動きを目撃した際、連絡をもらえる可能性が高まります。
対策2:郵便物の対策
郵便物や新聞などが溜まると、留守であることが外からわかりやすくなってしまいます。お盆の期間中は配達を停止するか、信頼できる人に受け取ってもらうようにしましょう。
対策3:窓とドアの確認
窓やドアはしっかり閉め、鍵をかけることが重要です。さらに、貴重品などは安全な場所に保管するとともにカーテンを閉めるなどして室内が外から見えにくくすることも必要です。
また、窓やドアは侵入手口のトップ1~3に入る箇所です。「確実な施錠を心掛ける」以外に、
- ガラス破りに強い窓にする
- 錠破りに強いドアにする
ことも検討しましょう。
外構・エクステリアによる防犯対策
敷地内もしっかり防犯対策しておきましょう。
対策1:建物に近づきにくくする
自宅への侵入者を防ぐために、まず大切なことは敷地内に侵入経路を作らないことです。オープンな外構がおしゃれで開放感がある一方で、人々が気軽に近づける環境を作ってしまうというデメリットもあります。侵入者が隠れやすいような植栽や高い塀がないかチェックしてみてください。敷地内が開放的であるということは、逆に言えば侵入者が隠れる場所が少ないともいえます。
特に家の裏手など、人目がなかなか届かないところには、センサーライト(照明)によるライティングが有効です。センサーライトは人の動きを感知して自動的に明るくします。家の周りの侵入者を助け、周囲からの視線を遮断してしまう暗闇にすることは、防犯上、あまり望ましくありません。しかし、このセンサーライトが夜間に人の動きを感知して照らすことで、侵入者を威嚇することができます。
さらに、防犯カメラの導入もおすすめです。防犯カメラは、不審者を撮影し、警察に提供することができます。また、カメラが見える位置に設置することで侵入者を抑止する効果もあります。外壁や軒下などにカメラが設置できない場合は、ポールを建て、カメラを取り付ける必要がありますが、最近では、安価で簡単に設置可能な防犯カメラが多く販売されていますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
対策2:侵入者の隠れ場所を作らない
敷地内にウォール(壁)としてブロックや高い植木を設置すると、それが視界を遮り、不審者に隠れる場所を提供してしまうことがあります。庭やエントランスの見通しを良くするようなデザインを心掛けることも外構の防犯対策として重要です。
侵入者は「見られる」ことで犯行を思いとどまるものです。つまり、窓や出入口の見通しを良くすることで、ガラスを割っての侵入やピッキング(鍵のこじ開け)などの犯行を防ぐ効果が期待できるのです。ただし、植木鉢やプランターなどを置くと、侵入者とは別に、留守中に持ち去る人も現れるので注意が必要です。
対策3:外構・エクステリアで侵入を防ぐ

外構やエクステリアの商品選びは、見た目の美しさだけでなく防犯効果も考える必要があります。カーゲート、フェンスなどを工夫して設置することで、不審者の侵入を防止することが可能です。
例えば、敷地全体を囲むようにフェンスを設置すれば、侵入者が簡単に中に入ることを防止し心理的に侵入をためらわせる効果も期待できます。これらの外構・エクステリア商品は、専門の施工会社に依頼すれば、自分の希望に合わせたデザインで設置することが可能です。
その他にも、門扉を設置することで、家への直接のアプローチを遮断します。
門扉の防犯効果:外構・エクステリアによる安全対策

自宅の防犯策としての「門扉」は、おしゃれな外観デザインだけなく、実際の防犯にも非常に効果的です。
門扉の防犯対策とそのメリット
門扉の防犯対策は、不審者の侵入を防ぐだけでなく安心感を得るための大切なポイントです。門扉があるだけで侵入者に対する心理的なバリアを作ることができます。また、見た目の良さを損なわずに防犯性を高めるためには、門扉のデザイン選択が重要。おしゃれなデザインであれば、家の外観を高めながら安全性も確保できます。一般的な施工例としては、木製の門扉が人気でナチュラルな外観が得られるほか、ブロックウォールに組み合わせた鉄製の門扉もまた人気で、とてもおしゃれで高い防犯効果を発揮します。
さらに、敷地内のプライバシーを保つための手段もあります。門扉がないと、人々の視線が直接家の中に入ってしまいます。これは、自分の生活を見られるストレスだけでなく不必要な侵入の可能性をもたらすこともあります。しかし、門扉があれば、これらの悩みを大幅に軽減できます。特に子供がいる家庭にとっては、門扉があることで子供が見られることなく遊べる空間を確保することができます。
門扉の種類
門扉には様々なタイプがあります。伸縮式や勝手口用など、ご自宅の建物や土地の形状や生活スタイルに合わせて選ぶことができます。どの門扉も、それぞれに特有の防犯効果があります。また、防犯効果をより高めるために、門扉に防犯カメラや防犯センサーを設置することも可能です。
これらの防犯商品を活用することで、より安全な生活空間を確保することができます。ただし、施工の際には、希望をかなえてくれ、信頼できる外構・エクステリアの専門会社に依頼することが重要です。
門扉の設置
門扉は、新築時の設置だけでなく、既存の戸建て住宅にも後付けできます。設置工事は専門の会社に依頼するのが一般的ですが、一部の商品はDIYで設置可能なものもあります。設置費用はタイプやデザイン、工事を必要とするかどうかによりますが、一般的には数十万円から数百万円程度掛かりますので、後悔しないためにも、専門的なアドバイスを受けつつ選びましょう。
防犯対策としての門扉の選び方
門扉選びのポイントは、防犯性能とデザイン性のバランスを保つことです。視線を遮るための門扉であれば、目隠し効果の高いものを選ぶと良いでしょう。しかし、完全に視線を遮ると、反対に不審者に利用される可能性もあります。見通しが確保できる範囲で視線を遮る門扉を選ぶことをおすすめします。
さらに、照明によるライティングも組み合わされると、より効果的な防犯対策となります。明るい光は、不審者を遠ざけるだけでなく、家の外観を引き立てる効果もあります。また、材質も防犯性に影響します。木製は自然な雰囲気を演出できますが、強度や耐久性に劣る可能性があります。一方、金属製は強度があり、長期間使用できるメリットがあります。
お盆前はエクステリア工事の駆け込みが多い
お盆前は、工事の依頼が殺到しがちです。早めの計画と信頼できる専門の施工会社業者の選択は、後悔しないためにも大事なポイントになります。
お盆前に工事依頼をする人が多い理由
お盆前にエクステリア工事の依頼が増える背景には、3つの主な理由があります。
- お盆に家族が集まるから
玄関や門扉、庭やガレージなど、見た目に関わる外構が整っていると、お盆に集まる来客を心地よく迎えることができます。外構をきちんと整えて迎えたいと思う人が多いため、工事依頼が集中しやすくなります。 - お盆が一年のひと区切りになりやすいから
夏休みが終わり、新学期や新生活を迎える前に、家の外構をリニューアルしたいと考える方も多いようです。 - 外構・エクステリア業者がお盆休みを取るケースが多い
お盆期間中は多くの外構・エクステリア業者も休みになります。そのため、工事を希望していてもお盆期間中は進まないので、その前に依頼を出す人が多いようです。
お盆前の工事依頼における注意点
しかし、お盆前に駆け込む工事依頼には注意が必要です。
- 希望スケジュールで工事できない可能性がある。
工事依頼が集中すると、予定が埋まってしまう可能性があります。そのため、早めの依頼が必要です。 - 工事の品質に影響が出る可能性がある。
依頼が殺到すると、工事を急ぎ過ぎてしまう可能性もあります。品質を確保するためにも、焦らず計画的に進めましょう。 - 費用が高くなる可能性がある。
需要が高まると価格も上昇する傾向があります。予算をしっかりと計画することが大切です。
駆け込みが予想される時期に、外構・エクステリア工事を行う際には、後悔にならないよう、これらのポイントを心に留めておきましょう。
まとめ:オープン外構の侵入防止と防犯対策
オープン外構という選択は、スタイリッシュな佇まいと開放的な雰囲気が楽しめて、何物にも替え難いものかもしれません。でもその一方で、安全性を決して疎かにしてはなりません。本記事でご紹介した防犯対策の施工や適切なフェンス、門扉の選択は、おしゃれと安心が共存する空間を築くための大切なピースです。
また、お盆前のエクステリア工事の駆け込み依頼は、望んでいるように進まないことがあるかもしれません。クレームとなってしまないよう、事前に、希望するイメージや商品を考え、施工スケジュールなど、先に計画を立てて、余裕を持つことが後悔せずに済む一番の近道になります。